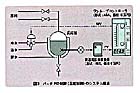温調計など簡単なコントローラの場合は、PID制御機能しかもっていないため、別にPLCを用意してシーケンス制御を行わせ、それらの動作をリレーで切り換えることが必要です。
エム・システム技研のワンループコントローラ(形式:ABA)では、PLCを使用せずにABA1台でバッチPID制御を実現できます。この点が一般のワンループコントローラと大きく異なる点です。もちろん、工業計器メーカーが発売している大形のPLCを使用するならば、1台で実現することが可能ですが、非常に高価です。
しかし、エム・システム技研のワンループコントローラ(形式:ABA)は、温調計と同等程度の低価格で大形PLCの機能が実現できるわけです。
それでは、バッチPID制御のシステム構成法について説明します。
7.バッチプラント
バッチプラントとは、図2のように原料を反応釜で反応させながら中間原料を経て製品へと仕上げて行くものです。
連続プラントとバッチプラントとは、次の点が異なります。
連続プラント
●すべてがパイプラインで接続されている。
●24時間稼働で停止することがない。
バッチプラント
●プラント間はパイプラインで接続されているが、バルブで仕切られている。
●反応釜を使用するときだけ稼働する。
●プラント間に必ず中間タンクがあり、中間原料が製品になる途中で保存される。
これ以外に連続バッチプラントというものもあります。これは、同じ反応をさせるバッチプラントを複数用意し、その前後には連続プラントが接続されています。
バッチプラントでは、反応釜単位でしか稼働できないので、1つの反応釜が稼働できない間は、他の反応釜が中間原料を製造して行くことになります。
ここでは、バッチPID制御を実現するにあたってワンループコントローラ(形式:ABA)の基本形PID制御機能を使用する方法に絞って説明します。もちろん、ABAのもっている拡張形PID機能を使えば、さらに複雑なバッチPID制御システムも構成できます。
8.反応釜におけるバッチPIDの使用例
(1)温度コントロール
図3はバッチPID制御を行うときのシステム構成例です。
ここでは原料を仕込み終わった後、反応釜で反応させます。反応中の温度をコントロールするため、反応釜のジャケットに流す冷水と温水の流量を3方弁で切り換えて温度をコントロールします。
反応の初期では、MV値による弁開度の調節だけで温度を上げて行きますが、目標値(SV)に近づくとPIDコントロールを行います。そしてこれ以後は、バッチ終了までPIDコントロールを続けます。
(2)ブロック接続例(図4参照)
次に、ABAに設定するパラメータとブロック接続の例を、この温度コントロールのうち、反応初期の部分に限って説明します。この設定は、パソコンとビルダーソフト(形式:SFE)あるいはプログラミングユニット(形式:PU-2A)を用いて行います。
G 02:基本形PID
ITEM53:80.0
これはプリセット値です。バッチ開始の弁開度値を入力しておきます。複雑な制