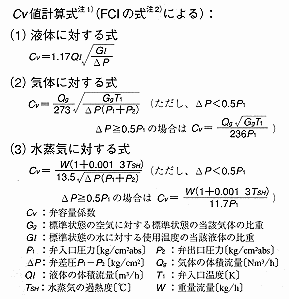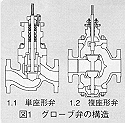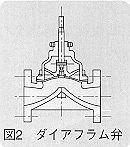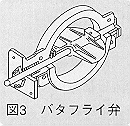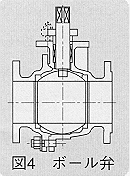| ●Cv値計算式 調節弁のCv値の計算式は、流体の種別(液体、気体、水蒸気)によって異なります。それぞれの計算式を以下に示します。いずれの式においても、流量が一定であるとすれば、Cv値が弁前後の差圧の平方根の逆数に比例し、反対にCv値が一定であれば流量が差圧の平方根に比例することが分かります。このことから、調節弁の原理が可変絞り機構であることが理解できます。
●固有レンジアビリティ 調節弁の弁容量の可変範囲を示すものであり、 R=Cv max/Cv min=Q max/Q minで表されます。調節弁による制御範囲の指標になります。 ●各種調節弁 調節弁には、基本構造の違いにより各種の形式があります。基本的には、弁軸の運動方式からリニアタイプとロータリータイプに分類できます。以下にその代表的な形式と特徴について説明します。 ①グローブ弁(図1参照) 調節弁の中でも最も一般的に使用されます。球状の弁本体を持ち、出入り口の中心線が一直線上にあります。構造から単座形弁と複座形弁があります。流量特性はイコールパーセンテージもしくはリニアで、レンジアビリティは30~50:1程度です。全レンジに渡り制御性に優れた調節弁です。 ②ダイヤフラム弁(図2参照) サンダース弁とも呼ばれます。弁本体の中央にせきを持ち、ダイヤフラムによって開閉します。スラリ流体などの制御に適しています。流量特性はリニアに近く、レンジアビリティは10~15:1程度ですが、低流量域での制御性はあまりよくありません。 ③バタフライ弁(図3参照) 弁本体内でディスクが回転して開閉します。構造がシンプルで、大口径の弁でも比較的安価です。流量特性はイコールパーセンテージに近く、レンジアビリティは20~30:1です。完全閉止時の漏れゼロも可能です。 ④ボール弁(図4参照) 弁本体内に穴の明いたボールを入れ、これを回転させて開閉します。閉止時の漏れが少なく(完全締め切りも可)、遮断弁として多く用いられますが、ボールにV字の切り込みを入れて特性を改善し、調節弁として用いることもできます。その場合の流量特性はイコールパーセントに近く、レンジアビリティは100~300:1と大きくなります。 ■ 〈参考文献〉オーム社「計装システムの基礎と応用」 注1)Cv値計算式は慣用的に用いられるため、SI単位系ではなく、旧単位系のままで示します。 注2)FCI-62:Recommended Voluntary Standard Formulas for Sizing Control Valves
|
| ||||||
|