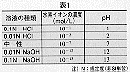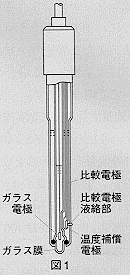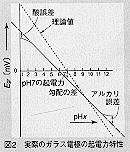| 2000年8月号 | ||||||||
計装豆知識pH計(1) | ||||||||
| pH計とは水溶液の酸性アルカリ性の程度を測る計器で、(社)日本分析機器工業会の統計によれば、とびぬけて生産台数が多い計測器です。pH測定の用途は非常に広範囲で、工場における製品製造の工程管理から、工場排水や河川水の公害監視に至るまで様々です。また形状についても、使用形態に対応して、ハンディ型、卓上型、定置型などがあります。 測定方式としては、指示薬式、アンチモン電極式、ガラス電極式などが実用化されています。 1.pHとは 従来の表現によれば、pHとは水溶液中の水素イオン(H+)濃度を表わす単位であり、希薄溶液ではpH=-log10(水素イオン濃度)と定義されていました。 水素イオン濃度の実例は、表1に示すように中性では10-7mol/L、0.1NのHClでは10-1mol/L、0.1NのNaOHでは10-13mol/Lとなり、非常に小さい数で実用上取扱いが煩雑になります。そこで、濃度の対数をとりマイナスの符号をつけると、それぞれ1、7、13と簡単な数値になるので、この単位をpHとしています。 2.JISの改訂 pH測定に関して、1983年から1984年にかけてJIS規格に大きな変更が行われました。変更されたのは、pH測定方法(JIS Z 8802)とpH標準液の規格(JIS K 0018~0023)であり、これによって測定方法がガラス電極法に限定され、pHは、pH標準液によって目盛り付けされた(校正された)pH計で測定された値と考えてよいことになりました。 3.ガラス電極法 ガラス電極法とは、水溶液のpHに比例した起電力を発生するガラス電極と、電位測定のための基準電位を与える比較電極を一対にして試料水に浸したとき、両電極間に発生するpHに対応する起電力を出力するpH電極と、目盛り付けするための機能を有しているpH指示変換器とを組み合わせて測定する方法です。比較電極には内部液(KCl溶液)が入っていて液絡部から少量ずつ流出させる構造をとっているため、内部液の定期的な補充が必要です。 3.1 pH電極 pH電極の起電力の理論値は、水温25℃では、1pH当たり59.16mVであり、温度が変化すると1℃当たり0.198mV変化します。これを補正するため、多くのpH計には温度補償電極が組み合わされています。そして現在は、ほとんどの電極が、ガラス電極、比較電極、温度補償電極を一体にした、扱いやすい複合型の電極構造を採用しています。 複合型pH電極の構造例を図1に、pH電極の起電力特性を図2に示します。 ガラス電極pH計では、pH1からpH13の間でpH値と電極電位差(検出器出力)とが、ほぼ直線の関係にあります。なおpH1以下では酸誤差、pH13以上ではアルカリ誤差のため直線性が悪くなっています。 ■
〈参考文献〉計量管理技術双書 「新版pH測定」 山下 熈(ひろむ)著 コロナ社 工業用水(昭和51年7月)「pHの測定とpH計の管理」伊東 哲 著
|
| |||||||
|
||||||||