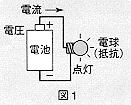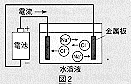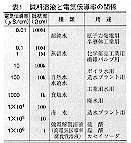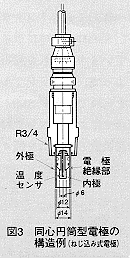| 2000年12月号 | |||||||||||
計装豆知識電気伝導率計のはなし | |||||||||||
このとき、電球がもつ電気抵抗(単位:Ωオーム)に対し、電流(単位:Aアンペア)を流そうとする電池の+、-端子間の電位差を電圧(単位:Vボルト)といい、電圧(V)=電流(A)×抵抗(Ω)という数式で、この関係を示したのが「オームの法則」です。
電極間の抵抗をRとすると、 L:電極間の距離(m) S:電極の面積(m2) κ:電気伝導率(m/s)
水溶液での電気伝導率は水質の良否を判断する指標であり、測定が簡単なことからいっても大切な測定項目として取り扱われています(表1参照)。表1は様々な水および水溶液の電気伝導率と抵抗率を示しています。純粋な水は絶縁体であり溶解する様々な電解質とその量により、電気伝導率が大きく変化することがわかります。 電気伝導率測定用の電極は、2枚の金属板を平行に配置した単純な形状だけでなく、用途に応じて様々な形状のものがあります。図3は、電極を同芯状に配置して、配管継手などにネジ込むようにしたプロセス用電気伝導率計の電極構造を示しています。 ■
|
| ||||||||||
|
|||||||||||