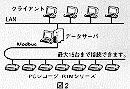| 2000年9月号 | |||||||||
Interface & NetworkNo.5 | |||||||||
| 本文の内容に関してご質問やご要求がありましたら、ホットラインフリーダイヤル
0120-18-6321 にてお気軽にお申し付けください。 ホットラインEメールアドレス hotline@m-system.co.jp | |||||||||
リモートI/O製品に関する市場状況については、本誌の本年5、6、7月号の各種関連記事の中で触れてきました。 エム・システム技研の関連製品としては、R1Mシリーズ(図1)、M9シリーズ、60・UNITシリーズなどが挙げられます。とりわけ、R1MシリーズとPCレコーダに対する反響は大きく、お問合せ、お引合いなどを多数いただいています。その中の一つに、「PCレコーダが処理できる点数は最大32点だが、それを超える場合は、パソコンでどのように処理すればよいのか?」というご質問がありました。 方法は次の2通りあります。 (1)Modbusプロトコルに従って通信処理するプログラムを、ユーザーが作成する。 (2)Modbusプロトコル対応ドライバを有する市販の監視・操作ソフト(例:富士電機インスツルメンツ社製「CITECT」)を使用する。 R1Mシリーズは、RS-485ケーブルで最大15台まで接続できます(図2)。 R1Mシリーズは、Modbusプロトコル対応になっており、パソコンでModbusプロトコルに従ってプログラム処理を行えば、R1Mシリーズとの間でデータ通信ができます。 Modbusプロトコルについては、本誌1999年11月号の「計装豆知識」に詳しく述べられていますが、概要は以下のとおりです。 Modbusプロトコルは、Modicon Inc.(AEG Schneider Automation International S. A. S)がPLC用に開発したプロトコルです。Modbusプロトコルで定義されているのは通信プロトコルだけで、通信媒体などの物理レイヤは規定されていません。R1MシリーズではRS-232およびRS-485、M9リモートI/OシステムではRS-232、RS-485/422およびEthernet、60・UNITシリーズではRS-485を介してModbusプロトコルを適用しています。エム・システム技研製品用Modbusプロトコルの詳細については、「Modbusプロトコル概説書(NM-5650)」をご参照ください。
ニッテツ北海道制御システム株式会社 計測制御部 江下 敦久 様 〒550-0087 北海道室蘭市仲町12番地 新日鐵室蘭製鐵所内 TEL:0143-47-2648 FAX:0143-47-2797 URL:http://www.ncsfox.co.jp E-mail:at_eshita@ncsfox.co.jp 設 立:1988年4月 資本金:8,000万円 社員数:約330人 新日本製鐵室蘭製鐵所のFA機器・電子回路設計および画像処理グループが独立し、直営事業体として発足した「室蘭計測センター(MKC)」、それにEICN(電気・計装・計算機・非破壊検査)エンジニアリング・整備グループを加えて設立されたのが、ニッテツ北海道制御システム(株)です。製鋼プロセスで長年にわたって蓄積してきた「制御技術力」が、その基盤になっています。 設立後は、各種製造業の設備・操業・原材料・製品品質にかかわる省エネ・コスト低減・品質改善(歩留り向上)など多くの課題に対して提案・実行し、解決してきました。このようなフィールドに密着した「計測制御システム」の一つとして、MsysNet計装部品を構成部品とし、監視・操作ソフトにはインテルーション社製FixDmacsを採用したパソコン計装システムが鉄鋼、電炉等で稼動しています。 今後も、エム・システム技研のMsysNet製品やリモートI/O製品に注目して行きたいと考えています。 ■ *MsysNetはエム・システム技研の登録商標です。
|
| ||||||||
|
|||||||||