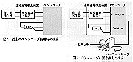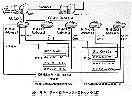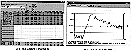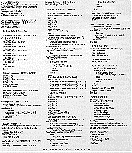| 2001年2月号 | |||||||||||||
エム・システム技研社内での
| |||||||||||||
| 株)エム・システム技研 製造部長 / 製造部生産技術G | |||||||||||||
使用方法としては、ペンレコーダをそのまま置き換えるのが標準的であり、付属品としてご提供しているPCレコーダソフト(形式:MSR32)をご利用いただくと、すぐに稼働させることができます。 また、MSR32に代わるプログラムを自作することによって、その利用方法は飛躍的に広がります。 今回は、エム・システム技研社内で専用プログラムを別途製作したPCレコーダ「R1M」の利用例についてご紹介します。
記録内容は、被検査品(製品)1台につき、出力値と周囲温度の2点です。 図2には、このペンレコーダをPCレコーダに置き換えた構成を示しました。 図1、図2からおわかりのように、信号発生器や連続通電検査装置自体には何も手を加えず、ペンレコーダをPCレコーダ「R1M」に置き換えた結果、次のような新しい、便利な機能が実現できました。 ①ペンレコーダ使用時には、ペンレコーダの測定レンジを人間がいちいち設定しなければならなかったのに対し、製品の機番(バーコード)を読み取るだけで、「R1M」の入力を自動設定できる。 ②ペンレコーダが記録したデータ(チャート紙)を見て、人間が良否判断していたのに対し、データを自動判定できる。 ③グラフは、必要なときにだけ画面で確認できる。 ④ペンレコーダでは記録紙を保存していたのに対し、電子データとしてサーバに保管できる。
そのデータに対応して、工程の中で製品1品1品に製造機番を振り当てています。製造ラインでは、この機番がキーとなり、バーコード化して製品とともにラインを流れて行きます。 今回は、この機番を利用してPCレコーダ「R1M」を使い、連続通電検査装置を改造しました(図3)。 連続通電検査装置を管理するパソコンに、バーコードを入力することにより、被検査製品の仕様をサーバから読み込み、RS-232-Cを通してPCレコーダ「R1M」にそのデータを送り、レンジ設定を自動的に行います。 検査中の確認画面としては、点数が多いことを考えて独自の画面(図5)を作成し、グラフは必要なときにだけ表示するようにしました(図6)。 検査結果の判定に必要な規格としては、従来から使用しているマスタを参照し、上下限値を設定しています。検査データは、パソコンを介し、製造部のサーバに機番をキーにして保存されます。後日、このデータはどこのパソコンからでも見ることが可能です。 このように改造することによって、単にペンレコーダがPCレコーダに置き換わるだけでなく、現在ある機能と連結して、非常に効率の良いシステムに変身できることがおわかりいただけたと思います。
図4に実際のR1M用データロガーソフト設計のシステム図を示します。 プログラムは全体を書くと長くなるため、R1Mとの通信部分だけを取り出し、図7に示します。
近い将来、MKセミナーでも利用方法の実習を行う予定であり、ご参考にしていただければ幸いです。 なお、PCレコーダ「R1M」についてご質問、ご意見等ございましたら、エム・システム技研ホットラインまでどうぞご連絡ください。 ■ |
| ||||||||||||
|
|||||||||||||