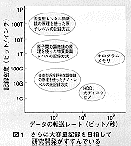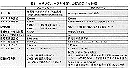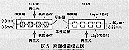| 2001年2月号 | |||||||||
温度のお話第10回 プラズマディスプレイパネル(PDP) | |||||||||
| (有)ケイ企画 代表取締役/エム・システム技研 顧問 西尾 壽彦 | |||||||||
温度の話から少し脱線して、マルチメディア市場を広げるパッケージメディアの中核商品であるDVDの市場動向と、その要素技術の概要についてご紹介しましょう。
動画の圧縮・再生の符号化方法にMPEG2(Moving Picture Experts Group Phase 2)を使うことで、現在のテレビ放送やVTRよりも高画質で、レーザディスク(LD)程度の画質を実現させています。 DVDは可変転送速度の技術を利用して圧縮した映像データを格納し、動きの激しい映像のときは符号化速度を高め、逆に動きの少ない映像では符号化速度を遅くして画質を維持しながら再生時間を延ばします。 デジタル記録では、再生時のデータ転送速度と映像の符号化速度は独立に設定でき、映画1本分の再生時間を確保しています。 MPEG2で圧縮した映像情報を伝えるパッケージメディアとして、またコンピュータ用の記録媒体として、DVDには大きな市場が目前に広がっています。 また、再生専用だけでなく追記型、書換型の開発も進んできました。 1-1 DVDの高密度大容量化技術 大容量化のポイントは以下の2点です。 イ)光ディスクシステムの光学系を改善することでCD、CD-ROMより高密度記録を実現している。 ロ)MPEG2を使って映像を圧縮・伸張することで大容量記録を実現している。 1-2 世界の電子工業の重要な基地、日本 DVDが今後のマルチメディア市場で記録媒体の中核となる機器であることは間違いなく、各電機メーカーが競っているのは当然といえます。 電子機器の開発・設計に勝れている日本は世界の電子工業にとって重要な基地であり、エネルギーと並んで電子機器は近代産業を支える戦略物資であるといわれています。 この日本メーカーによるDVDの開発と世界市場への供給が大いに期待されています。そして、表1にあるようにソニー・フィリップスグループと東芝および日本のその他のメーカーグループの2グループが激しく争っており、規格統一が円滑に進んでいないために障害が生じていることは周知のとおりです。 1-3本命のマーケット コンピュータ向けのDVDでは、データの書き換えが求められています。 図1に示す方向で、高記録密度、高速読み出しを実現する次世代の方式や媒体などの研究が進められています。課題は大容量記録とデータ読み出しの高速化です。 これらの研究がDVDの適用対象として狙った市場は、当初は映像市場であり、米国の映画産業の支持を得るために、日本メーカーがハリウッド詣でをしたものです。 その後、時間を経て現状では、本当に大きい市場はコンピュータ周辺機器であり、DVDの真のターゲットはマルチメディアパソコンで再生する映像や音声を提供するパッケージメディアであるといわれています。 さらに、ハイビジョン並の画質を実現させるハイビジョンデジタルテレビDVDを実現するためには、容量10Gバイトの光ディスクおよび短波長青色レーザの実用化が待たれます。
光ディスクの記録密度を高めるには、読み取りレーザ光の波長を短くすることが欠かせません。 現在の青色半導体レーザには、実用化に際してなお不十分な点があります。次善の策として、赤色レーザ光の波長を光学素子を使い短波長化することによって青色レーザを発生させるSHGブルーレーザの実用化研究が進んでいます。 図2に示すように、対物レンズにより集光されるレーザ光の集光スポットの大きさ(D)は、レーザ光の波長(λ)に比例し、対物レンズの開口数(NA)に反比例します。 このため、青色半導体レーザが実用化されるまでの間は、現在入手可能な赤外線波長の高出力半導体レーザを基本波長として使用し、非線形光学材料により第2高調波を発生させ(SHG-Second Harmonic Generation)、1/2波長に変換することで青色レーザ光(425nm)を得る方法がとられることになります。 素子の安定した発振を保証するための温度制御やノイズレベルの低下を図るための温度設定など、各種の温度依存性についての説明は、ここでは省略しますが大変重要な要件です。図3、図4には、関係する参考データを示しました。 2-2 2層ディスク SD規格(東芝グループ規格)では、9Gバイトの厚さ0.6mmの2枚のディスクを貼り合わせた「片側読みとり方式2層光ディスク」が実用化されています(図5参照)。 ディスク製造のポイントは「半透明膜の形成」と「透明接着剤による貼り合わせ」の技術です。 紫外線硬化樹脂による膜形成などは、高分子材料の乾燥、硬化、アニールなどすべて優れた熱処理の下に完成できるものです。 ■ ◆ 参考文献 ◆ 日経ニューメディア別冊 「最前線レポートDVD」 |
| ||||||||
|
|||||||||