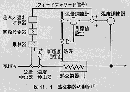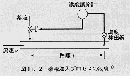| 1998年4月号 | ||||||||
自動制御入門 第13回
各種の制御手法(その1) | ||||||||
| 松山技術コンサルタント事務所 松山 裕 | ||||||||
| 11.各種の制御手法 この入門シリーズでは、これまでフィードバック・PID制御を前提として説明してきました。しかし、制御対象や制御の目的によっては、単純なフィードバック・PID制御ではうまくいかない場合があります。これは、フィードバック制御やPID制御に基本的な限界があるからです。このような限界を超えるため、各種の制御手法が考案され、実用化されています。 以下、上記の視点より、重要な制御手法について説明します。 11.1 フィードバック制御の限界と対策 フィードバック制御の限界としては、外乱の影響を早くなくせないことと、プロセスのむだ時間が大きいときハンチングすること(調節計の出力が周期的に大きく変動すること)が挙げられます。以下に、その理由と対策を説明します。 (1)外乱の影響を早くなくす制御手法 フィードバック制御では、外乱の影響が測定値の変化となって調節計に伝えられてから、初めて調節計は外乱に対する修正動作を起こします。プロセスには常に遅れがありますから、外乱が発生してから、測定値が変化するまでには時間がかかります。さらに調節計が修正動作信号(調節計出力)を出しても、プロセスの遅れのため、外乱による影響をなくすまでにはかなり時間がかかります。これはフィードバック制御の宿命ともいえるものです。この対策として、フィードフォワード制御があります。 もし外乱の大きさと、それが測定値に与える効果の度合がわかっているならば、ずばりこれに相当する信号を使って調節弁を操作すればよいはずです。これならば、フィードバック制御と違ってプロセスの遅れの影響がないので、外乱の影響を早くなくすことができます。やや突飛なたとえですが、料理を作るときいちいち味見をしながら少しずつ調味料を入れて行くのは時間がかかります。しかし、料理の本を見てレシピどおり最初から調味料を入れれば早くできます。味見しながら調味料を入れるのはフィードバック制御であり、レシピどおり一度に調味料を入れるのはフィードフォワード制御です。しかし、レシピどおりといってもまったく味見しないのは心配ですので、普通は最後に味見をして確認または修正を行います。フィードフォワード制御でも、これだけでは最終的に目標値どおりにならないので、フィードバック制御と併用します。 熱交換器における例を図11.1に示します。この図の熱交換器の目的は、供給原料液を加熱して一定温度にすることにあります。熱交換器が原料液に与えなければならない熱量は、(原料流量)×(温度目標値-原料温度)であることは明らかです。したがってこれらの流量や温度を測定し、演算器により所定の熱量を求め、これを熱媒流量調節計の目標値にすればよいのです。右側の温度調節計は、いわば念のためにつけたフィードバック制御系です。たとえば、熱交換器の汚れなどで熱媒から原料液への熱伝達が悪くなっても、フィードバック制御系があれば安心です。 なお、図11.1にある進み/遅れ演算器は、原料液の流量や温度の変動が熱交換器出口温度変化になるまでの時間と、熱媒の流量変化が熱交換器出口温度変化になるまでの時間を一致させるために必要です。 フィードバック・フィードフォワード併用制御方式の代表的な例は、ボイラドラムの水位制御ですが、その説明は省略します。 (2)むだ時間によるハンチングをなくす制御手法 まず、むだ時間が大きいプロセスにフィードバック制御を行うとどうなるか考えてみましょう。第4回の図4.4を図11.2に再掲して説明します。この例では配管の途中から薬液を注入し、下流側で濃度を検出し、濃度調節計によって薬液調節弁を操作します。仮に薬液注入量が少なく、濃度検出器で測定した値が目標値より小さかったとします。すると調節計は薬液調節弁を操作し、薬液注入量を増加させます。しかしこれによる濃度変化は、むだ時間に相当するl/υ時間後になって初めて調節計へ伝えられます。そのときの測定値は、通常は目標値をかなりオーバーします。するとまたこれにより調節計は調節弁をぐっと閉めることになり、このシーケンスが次々と続きます。この結果多くの場合、調節弁は全閉と全開を繰り返すいわゆるハンチング状態になります。 この対策としては、スミスのむだ時間補償制御とサンプルPI制御がありますが、ここでは前者について説明します。 スミスのむだ時間補償制御のブロック線図を図11.3に、制御の原理図を図11.4に示します。 説明の便宜上、対象プロセスの特性は、むだ時間+一次遅れであるとします。図11.4の(a)は、調節計出力がステップ状に変化したことを示しています。このときプロセスはこの調節計出力を受けて、図の(b)の出力を出します。(Lはむだ時間、Tは一次遅れの時定数)。一方むだ時間補償器は、ステップ状の調節計出力を受けて、図の(c)の形の出力を出すように作られています。この出力は、時定数Tの一次遅れと同じ特性で立上がり、むだ時間Lを経過したあとは、時定数Tの一次遅れ特性で下降します。図11.3に見るように、プロセスの出力(すなわち測定値)とむだ時間補償器の出力は、一緒に調節計にフィードバックされ、目標値と比較されます。すなわちPID調節計から見れば、図の(d)の形の特性(時定数Tの一次遅れ)のプロセスを制御するのと同じことになります。したがって制御は容易となります。 この制御手法は、1959年にスミスが発表した有名な方法です。しかしアナログ演算器しかない当時では、むだ時間補償器を作ることは困難でした。デジタル調節計が普及した現在では実現は容易であり、この機能を内蔵した調節計は容易に入手できます。 この方法を実施するには、プロセスの特性を等価むだ時間と等価時定数として測定すること、およびその2つの定数が変化しないことが条件となります。しかし、それらの定数が変化するとしても、ほかの測定値との関係が既知であれば、この制御手法を適用できる場合もあります2)。 ■ ◆ 参考・引用文献 ◆ 1)松山 裕:だれでもわかる自動制御、省エネルギーセンター(1992) 2)村上 良明:スーパーDCSによる適応形むだ時間補償制御、エムエスツデーVol. 5、No. 12、p. 6~7(1996) |
| |||||||
|
||||||||