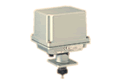「ステップトップ®」を使った電動調節弁が紙・パルプ工場で採用された事例のアプリケーション内容を紹介し、「ステップトップ®」の持つ特長がどのように活かされているかについて解説します。
計装豆知識
調節弁の基礎知識(1)
印刷用PDF エムエスツデー 2000年5月号
はじめに
調節弁とは、一般にプロセス設備の配管の途中に挿入され、液体、蒸気、気体などの流体を通過させたり、遮断したりする機構部を指します。調節弁は、流体に直接触れて流量 を制御する内弁(絞り機構)を持つ調節弁本体と、制御信号(操作信号)に応じて調節弁本体の内弁を動かすための駆動部(アクチュエータ)により構成されます。調節弁の種類は、駆動部の動力源によって、空気圧式調節弁、電気式(電動式)調節弁、油圧式調節弁、自力式調節弁などに大別されますが、本稿では空気圧式調節弁と電気式調節弁に的を絞って解説します。
図1に、調節弁の代表的な例として、空気圧式調節弁(グローブ弁)の構造図を示します。

調節弁本体の諸特性
調節弁本体(以下、調節弁とします)には、中枢となる内弁(絞り機構)の構造の違いによって様々な種類があります。その解説は次号以降で行いますが、ここでは先ず、各種の調節弁に共通して定義される、特性や性能を示す重要な項目について解説します。
•弁サイズ
一般に、弁サイズとは調節弁の接続口径や内弁(絞り機構)の口径のことを指しますが、広義には調節弁の大きさ(容量)を意味します。必要な流量を得るために適切な弁サイズを選定することを、サイジングといいます。調節弁の容量は弁の接続口径や内弁の口径だけではなく、弁本体や流体の種類などによって大きく異なります。そこで、これらを包括して弁の容量を一義的に表す指標として、Cv値があります。Cv値の定義を以下に示します 注)。
Cv値:調節弁の容量を示す数値であり、弁の開度を一定にし、その前後差圧を 1psi に保ち、60°F の水が1分間に流れる量をUSガロンで表した値で示されます。たとえば、弁差圧 1psi で10USgal/min の水を流すことができるとき、Cv値は10であるといいます。
通常、調節弁の仕様として表示してある定格Cv値は、最大値(弁が全開のときの値)を意味します。サイジングに当たっては、対象となる調節弁の流体条件(液体・気体・水蒸気)に基づき、Cv値を算出し、その値と比較して、適切な定格Cv値を有するサイズの調節弁を選定します。
それぞれの流体条件に対するCv値の計算式については、次号にて説明します。
•固有流量特性
弁前後の差圧が一定に保たれている場合の開度(0~100%)と対応する流量 の関係を、調節弁の固有流量特性といい、主なものとして下記の3種類があります(図2参照)。

① クイックオープン特性
② リニア特性
③ イコールパーセント特性
一般的に、流量制御用としては ②、③ もしくはその中間の特性の調節弁が用いられます。① はオン・オフ弁として用いられます。
注)Cv値は慣用的に用いられるため、SI単位系ではなく、旧単位系のままで示します。
(株)エム・システム技研 システム技術部
調節弁の基礎知識(2)
印刷用PDFエムエスツデー 2000年6月号
•Cv値計算式
調節弁のCv値の計算式は、流体の種別(液体、気体、水蒸気)によって異なります。それぞれの計算式を以下に示します。いずれの式においても、流量が一定であるとすれば、Cv値が弁前後の差圧の平方根の逆数に比例し、反対にCv値が一定であれば流量が差圧の平方根に比例することが分かります。このことから、調節弁の原理が可変絞り機構であることが理解できます。

•固有レンジアビリティ
調節弁の弁容量の可変範囲を示すものであり、
R = Cv max / Cv min=Q max / Q minで表されます。調節弁による制御範囲の指標になります。
•各種調節弁
調節弁には、基本構造の違いにより各種の形式があります。基本的には、弁軸の運動方式からリニアタイプとロータリータイプに分類できます。以下にその代表的な形式と特徴について説明します。
① グローブ弁(図1参照)
調節弁の中でも最も一般的に使用されます。球状の弁本体を持ち、出入り口の中心線が一直線上にあります。構造から単座形弁と複座形弁があります。流量特性はイコールパーセンテージもしくはリニアで、レンジアビリティは30~50:1程度です。全レンジに渡り制御性に優れた調節弁です。

② ダイヤフラム弁(図2参照)
サンダース弁とも呼ばれます。弁本体の中央にせきを持ち、ダイヤフラムによって開閉します。スラリ流体などの制御に適しています。流量特性はリニアに近く、レンジアビリティは10~15:1程度ですが、低流量域での制御性はあまりよくありません。

③ バタフライ弁(図3参照)
弁本体内でディスクが回転して開閉します。構造がシンプルで、大口径の弁でも比較的安価です。流量特性はイコールパーセンテージに近く、レンジアビリティは20~30:1です。完全閉止時の漏れゼロも可能です。

④ ボール弁(図4参照)
弁本体内に穴の明いたボールを入れ、これを回転させて開閉します。閉止時の漏れが少なく(完全締め切りも可)、遮断弁として多く用いられますが、ボールにV字の切り込みを入れて特性を改善し、調節弁として用いることもできます。その場合の流量特性はイコールパーセントに近く、レンジアビリティは100~300:1と大きくなります。

<参考文献>
オーム社「計装システムの基礎と応用」千本 資、花淵 太 共編
注1)Cv値計算式は慣用的に用いられるため、SI単位系ではなく、旧単位系のままで示します。
注2)FCI-62:Recommended Voluntary Standard Formulas for Sizing Control Valves
(株)エム・システム技研 システム技術部
調節弁の基礎知識(3)
印刷用PDFエムエスツデー 2000年7月号
調節弁駆動部
調節弁駆動部(以下、駆動部と呼ぶ)とは、調節計からの操作信号を受け、その値に確実に対応した弁開度を得るために必要な駆動力を発生する機構部です。
駆動部は、動力源の違いによって、空気作動式、油圧作動式、電気作動式(電動式)などの方式に大別されます。これらのうち、現在では特殊な用途を除いて、空気作動式もしくは電気作動式が多く使用されています。
•空気作動式
構造が簡単であり、大きな駆動力が得られます。また、取り扱いも容易で、他の方式に比べて比較的安価であるため、最も多く使用されています。一方、空気には圧縮性があるため、精度、応答性には限界があります。また、動力源である圧縮空気を発生させるための空気源装置(コンプレッサ、脱湿機、フィルタなど)が大がかりになるなどの難点もあります。空気作動式駆動部の代表例として、ダイヤフラム式の構造図を図1(直線運動形)、および図2(回転運動形)に示します。

•電気作動式
動力源(電源)の入手は一般に容易であり、比較的小型ながら強力な操作力が得られます。また、原理上、高分解能(高精度)、高速応答性を特長としています。かつては、構造が複雑で、比較的高価であったため、市場での普及率が低かったのですが、近年は信頼性の高い、安価な電気作動式駆動部が数多く商品化され、年々需要が高まってきています。
電気作動式駆動部には、電動モータ式とサーボモータ式があります。電動モータ式は、主として中~大口径の弁に用いられ、ステータス信号によって開/閉動作を行います。サーボモータ式は、比較的小口径の弁に用いられます。弁開度をフィードバック制御する機構を備え、調節計からの操作信号に対応した正確な弁開度が得られます。また、操作信号に対する応答性も優れており、固有周期が短い制御ループにも用いることができます。
サーボモータ式の駆動部の例として、エム・システム技研製のサーボトップ 2(直線駆動タイプ、代表形式:PSN1およびPSN3)の外観および内部構造を図3、図4に示します。サーボトップ 2はマイクロプロセッサによるデジタル式開度制御機構を備えたステッピングモータ式駆動部です。弁に搭載後に、全閉・全開位置に現物合わせのうえ、その位置を全閉・全開位置として学習させることや現場で開閉速度の調整が可能であるなど、各種の設定調整が容易になっています。また、ブラシレス構造に伴う長寿命、さらに1/1000の高分解能など多くの特長を持っています。

おわりに
調節弁は制御システムにおける最終操作端として重要な位置を占めていますが、調節弁本体の機構は基本的に非常にシンプルなものです。それ故に、これまで長い間、革新的な技術の出現はほとんど見られませんでした。しかし、本稿で紹介した、マイクロプロセッサ搭載の駆動部や、さらに通信ネットワーク対応の駆動部(エム・システム技研もまもなく発売する予定)など、今後は電気作動式の駆動部を中心に画期的な進歩が予測されます。
(株)エム・システム技研 システム技術部
ご注意:当サイト「計装豆知識」は掲載誌発行当時の記事をそのまま再編集しておりますので、内容の一部(規格、価格、製品仕様など)が、その後変更されている場合があります。最新の情報や掲載記事に関するご質問はホットラインまでお問合せください。
関連ワード 一次遅れ
関連動画
 紙・パルプ工場向け電動アクチュエータ 「ステップトップ®」
紙・パルプ工場向け電動アクチュエータ 「ステップトップ®」 電動調節弁革命 空気圧式調節弁と電動調節弁の比較
電動調節弁革命 空気圧式調節弁と電動調節弁の比較空気圧式調節弁と電動調節弁を実際の流量制御ループに取付けて、それぞれの制御結果を具体的に見ていただきます。
 空気源装置が要らない ステップトップ® を使った電動調節弁
空気源装置が要らない ステップトップ® を使った電動調節弁空気圧式調節弁に必要な計装用圧縮空気を作る空気源装置とは実際にどのようなものであるかを分かり易く解説しています。そして空気源装置が不要な「ステップトップ®」を使った電動調節弁の特長を紹介します。
 電動調節弁に革命を起こす1/1000キット
電動調節弁に革命を起こす1/1000キット電動アクチュエータ ステップトップシリーズのデモンストレーションキットである1/1000キットの解説動画です。
関連製品