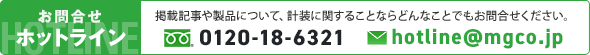センサ
- イオン電極のはなし/2001.3
- ORP(酸化還元電位)について/2001.4
- 温度センサ:サーミスタ/2006.11
- 温度センサの選択と設置(1)/1998.4
- 温度センサの選択と設置(2)/1998.5
- カルマン渦の話/1994.3
- コアレス電流センサ/2000.10
- CT(Current Transformer)について(1)/2008.07
- CT(Current Transformer)について(2)/2008.08
- ジルコニア式酸素濃度計の話/1994.7
- セルシン/2002.12
- 測温抵抗体の導線方式/2003.4
- 電気伝導率計のはなし/2000.12
- 電磁濃度計のはなし/2001.1
- 熱電対と熱電対信号変換器(1)/1998.6
- 熱電対と熱電対信号変換器(2)/1998.7
- 熱電対・変換器間の導線による温度測定誤差と対策/2012.10
- pH計(1)/2000.8
- pH計(2)/2000.9
- pH計(3)/2000.11
- ポーラログラフについて/2001.5
- 溶存酸素計のはなし/2001.2
- 流速計による流量測定方法/1996.3
- ロータリエンコーダ/2003.1
- ロードセルの仕組みと使い方/2018.1
エムエスツデー 1998年4月号
温度センサの選択と設置(1)
温度の測定では、高い精度のセンサと変換器を使用すれば、正しい温度の測定ができるとは限りません。測定対象に適したセンサを選ぶとともに、センサの取付け場所や取付け方法についても配慮することが必要です。熱電対、測温抵抗体、サーミスタなどのように、測ろうとするものに接触させて温度を測定する接触式温度計では、温度センサの温度と測定対象の温度が一致することがまず必要です。また、センサを設置することによって熱伝導などの条件が変わり、測定対象の温度が変わるため正しい測定ができないこともあります。
測定の遅れ
温度センサと測定対象の温度が一致するには、時間が必要です。温度変化が激しい測定では、遅れの少ない温度センサを選択する必要があります。同じ温度センサを使っても、測定対象の種類や条件によって遅れは異なります。たとえば、静止している気体の温度測定では、遅れは大きくなります。
正しい温度測定のためには、遅れの小さいセンサを用いるとともに、気体との熱接触をよくするため、接触面積を大きくするなどの対策が必要です。また可能であれば、気体をかき混ぜることが有効です。
温度センサを、一定温度の測定対象に接触させて温度を測る場合、測定対象とセンサの温度差が、センサを最初に測定対象に接触させたときの温度差の約1%になるまでには、測定遅れの時定数の約4倍の時間が必要です。
測 定 対 象
1.固体表面
固体表面の温度を測定する場合には、固体の表面にセンサの先端を接触させるだけでなく、センサからのリード線の一部も表面に接触させて、温度センサと同一温度に保つことが望まれます。
熱電対を用いる場合には、固体の表面との熱接触をよくするため、熱電対の先端を銅板などにろう付けし、銅板を固体表面に密着させるのも一方法です。また測定対象が厚いときには、表面に浅い溝を掘って、その中にセンサを埋め込む方法もあります。
いずれの場合も、温度センサを設置することによって、表面の温度が変わらないよう配慮する必要があります。
回転体や走行体などの表面温度の測定の際、スリップリングを使用するときは、摩擦熱など、測定対象以外からの熱の影響を受けないよう考慮する必要があります。
2.固体内部
固体の内部の温度測定では、対象物に穴をあけて、センサを埋め込むか挿入します。そのとき、センサと固体との熱接触をよくするために、熱伝導性のよい液体などを穴に入れることが望まれます。
3.気 体
気体の温度測定では、前述の遅れ対策のほか、直射日光に照らされる場合のように、放射熱の影響を受けるときには、放射遮断をすることが正しい温度測定のために必要です。
気体をかき混ぜられない場合は、数箇所の温度を測り、演算によって全体の温度を測る方法もとられます。また、気体と容器の温度は必ずしも一致しないので、容器や部屋の壁から離してセンサを取付けることも必要です。
高速で流れている気体の場合は、気体とセンサの接触によって熱を生じ、真の気体温度より高い温度を示すこともあるため、注意が必要です。